シリーズ目次(クリックで展開)
①吸血鬼の元祖はドラキュラではなく、吸血鬼ルスヴン卿こそが吸血鬼の始祖
②吸血鬼ドラキュラより古い吸血鬼小説はこれだけある
③この記事
④バイロンの吸血鬼の詩「異教徒」とバイロンの祖国追放
⑤『最初の吸血鬼』と『醜い怪物』が生まれた歴史的一夜「ディオダティ荘の怪奇談義」
⑥最初の吸血鬼小説と当時の出版事情の闇、それに翻弄される者たち
⑦ドラキュラ以前に起きた「第一次吸血鬼大ブーム」・大デュマの運命も変えた
⑧日本に喧嘩を売ったフランスの吸血鬼のクソオペラ
- 最初の吸血鬼小説の作者は、本人は無名だが親戚は有名
- 最初の吸血鬼の作者、ジョン・ポリドリ
- 事実は小説より奇なり:詩人バイロン卿
- 幼少期のバイロン卿:逆境にめげない主人公
- 放蕩三昧する大学時代のバイロン 男色にも目覚める
- バイロンの人生に大きく影響を与えたグランドツアー
- ある日、目が覚めたら有名人になったバイロン
最初の吸血鬼小説の作者は、本人は無名だが親戚は有名
前々回の記事で、最初の吸血鬼小説はジョン・ポリドリの「吸血鬼」という小説で、吸血鬼ルスヴン卿こそが最初の吸血鬼であると説明した。今回はその”最初の吸血鬼小説”を作り上げた、ジョン・ポリドリについて解説していこう。そしてポリドリを語るには、彼が侍医として仕えた、詩人バイロン卿も解説も必須。よって彼の主人、バイロン卿についても詳しく解説していこう。

(1795~1821) 日本語wikipedia 英語wikipedia
ジョン・ポリドリはロンドン生まれで、本業は作家ではなくて医者だった人物だ。だが作家にも憧れていたようで、今回紹介する「吸血鬼」を世に発表、吸血鬼のプロトタイプを世に送り出した。
さて彼を知ってる日本人は少ないだろう。実際、有名だとは言い難い。有名ならばドラキュラよりも、彼の名と作品「吸血鬼」の方が知られていないとおかしい。彼自身の日本語wikipedia記事と、彼の作品「吸血鬼」の日本語wikipedia記事が作られたのは2021年4月17日と、ごくごく最近ようやく作成されたぐらいだ。彼の作品「吸血鬼」の彼が文学的名声を得たのは、その作品の質よりも彼を取り巻く人々によってである、とまで書く書籍もある*1。この書き方で分かるように彼自身は有名ではないが、親族には有名になった人がいる。彼の甥に、ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティという人物がいる。ポリドリの妹・フランシスの息子がロセッティである。

ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ(英語wikipedia)
(1828~1882)
前回、前々回の記事では、吸血鬼の詩として「レノーレ(1773)」を紹介した。この作品自体は吸血鬼は出てこないが、民間伝承の吸血鬼と関係があるとされ、「吸血鬼ドラキュラ」の冒頭で引用するシーンがあることは、前回説明させてもらった通り。「レノーレ」は元はドイツ語の詩だがドイツ以上にイギリスにおいて有名になり、数多くの英訳が試みられた。その英訳で有名になったものは2つある。一つは詩人サー・ウォルター・スコットによるもの。もう一つがこのロセッティによるものである。ロセッティはわずか16歳にてこの「レノーレ」の英訳を手掛けて、一躍有名になったと言われている*2。荒俣宏・編「怪奇文脈大山脈1」:東京創元社(2014)に、南條竹則による「レノーレ」の邦訳が収録されているが、これはロセッティの英訳から重訳したものだ。余談になるが、小泉八雲は東京帝国大学の講師時代、ロセッティの文学作品は視点を変えて幾度も講義していたようだ*3。
だがロセッティは、現在はラファエル前派の画家としてのほうが遥かに有名だ。2019年10月~12月には、大阪・あべのハルカス美術館にて「ラファエル前派の軌跡展」が開かれており、ロセッティの絵が目玉として紹介されていた。


私が撮影したもの。撮影・公開可能ゾーンの展示物でした。
このようにポリドリの甥は美術界隈では大変有名になった。ついでなので、ロセッティの母やロセッティの兄弟たち、つまりポリドリの妹とその子供たちも紹介しよう。ポリドリのことからは脱線してしまうが、日本の書籍においては、ダンテ以外の親戚は紹介されることがないし、面白い情報もあるのでここで紹介しておきたい。


(1827~1876)
右側の画像は、弟ダンテ・ゲイブリエルによる肖像画。マリアはダンテ・アリギエーリに関する著書”The Shadow of Dante"を発表している。左側の写真で分かるように非常に丸顔なので、兄弟からは「ムーニー」と呼ばれて揶揄われていたようだ。叔父であるジョン・ポリドリとなんとなく似ていると思うのは、私だけだろうか。それはともかくとして、彼女はターナーやラファエル前派に多大な影響を与えた、美術評論家のジョン・ラスキンとは友人関係であった。

(1829~1919)
イギリスの作家で批評家。兄・ダンテ・ゲイブリエルと他の数名のメンバー共に、1848年に「ラファエル前派」を立ち上げ、英国美術界に多大な影響を与えた。ラファエル前派の同盟においては、主に書記を務めた。叔父ジョン・ポリドリは、バイロンと旅行したときに日記をつけておいて、それをいずれ出版する予定でいたのだが、そのポリドリの手記を編纂して発表したのが、このウィリアム・マイケルである。画家・作家・モデルとして活躍したルーシー・マドックス・ブラウンと結婚した。1911年版ブリタニカ百科事典の芸術分野の編集において、多大な貢献を残す。マイケルが編纂したポリドリの日記は後日、別の記事にて紹介しよう。

(1830~1894)
画像の肖像画は兄・ダンテ・ゲイブリエルによるもの。クリスティーナはイギリスの詩人。人道的な観点から、奴隷制や売春による性的搾取、動物実験に反対した。兄・ダンテ・ゲイブリエルをはじめ、ラファエル前派の画家たちに度々モデルにされている。彼女の詩もいくつか翻訳されている。そのためか日本語wikipediaにも記事がある(リンク先参照)。

クリスティーナをモデルとした、兄・ダンテ・ゲイブリエルの作品。
母・フランシスの影響も見て取れるとされる。

(1800~1886)
本国では著名となったロセッティ兄弟姉妹の母であり、最初の吸血鬼小説を作り上げたジョン・ポリドリの妹。ポリドリは度々フランシスに手紙を送っており、妹のことは何かと気にかけていたようだ。息子ダンテ・ゲイブリエルは、度々母フランシスの絵を描いていたようで、とくに初期の作品は、モデルとしてポーズをとっていたという。
夫はイギリスに移住したイタリアの貴族、詩人のガブリエーレ・ロセッティ。彼の詩は、ウィルキー・コリンズの小説「白衣の女」の登場人物ペスカの元になったと考えられている。また、19世紀前半にイタリアとフランスに興った革命的秘密結社カルボナリの創設者の一人でもある。そんな経歴なので彼もまた海外ではwikipedia記事が存在している。

ポリドリの妹・フランシス親子の写真が残っている。それが上の画像であり、フランシスの英語wikipedia記事に掲載されている。右から、長女マリア、次男ウィリアム、母フランシス、長男ダンテ、次女クリスティーナの順である。この写真を撮ったのはチャールズ・ラトウィッジ・ドジソン、作家として活動するときのペンネームは”ルイス・キャロル”と名乗っていたと言えば、お分かりになるだろう。そう、あの「不思議の国のアリス」の作者による撮影写真だ。先ほどのフランシスの個人写真も、ルイス・キャロル撮影によるもの。ルイス・キャロルはロセッティ家とは親交があった。こうしたロセッティ家の写真は、"あの"ルイス・キャロルの写真作品として紹介されるようだ。この写真やフランシスの肖像画等は、ロンドンの美術館ナショナル・ギャラリーの別館、ナショナル・ポートレート・ギャラリーに保存されている。ナショナル・ポートレート・ギャラリーで公開されている他の写真はこちら。
最初の吸血鬼の作者、ジョン・ポリドリ

閑話休題。今回主題のポリドリの話題に入ろう。ポリドリはイギリス人だ。だが肖像画を見て何となくわかるように、元はイタリア人の家系だ。ポリドリの祖父・アゴスティーノ・アンサノ・ポリドリは、ピサに住む医者兼詩人だった。『骨学 (Osteologia)』 という人骨についての奇妙な詩を1763年に出版している*4。アゴスティーノにはルイージとガエターノという二人の息子がおり、ルイージはアレッツォでチフス研究の権威となる。ガエターノは熱心なキリスト教徒。法律の勉強をし、悲劇作家ヴィットーリオ・アルフィエーリの秘書として働き、最終的にはイタリア語の教師としてイギリスに移住する。最初のゴシック小説とされるホレス・ウォルポールの「オトラント城奇譚」をイタリア語訳したのも、ガエターノである。そのガエターノの長男がポリドリだ*5*6*7。

(1763~1853)
上の肖像画を描いたのは勿論、ラファエル前派の画家であり孫のダンテ・ゲイブリエル・ロセッティである。ガエターノはプライベートプレス機を所有していたので、父アゴスティーノの詩「骨学」の他、孫のダンテやクリスティーナの詩の印刷もしてあげたようだ*8。ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティは、当初は詩人として活躍、とくにドラキュラでも引用された「レノーレ」で有名になったが、そのレノーレを印刷したのも、祖父ガエターノなのかもしれない。
さてこうした親から生まれたポリドリであるが、知人のハリエット・マーティノーに言わせると「美男だが、そそっかしい若者」であったという*9。確かに肖像画を見ても美男子であることが伺える。

(1802~1876)
マーティノーはイギリスの社会理論化でホイッグ党の作家、そして女性として最初の社会学者とされる。若き頃のヴィクトリア女王はマーティノーの著作を好んでいたそうだ。幼いころから味覚と聴覚を失っていき、とくに耳は聞こえなくなった。湖水地方に移り住み、詩人ワーズワースと友人関係になる*10。そして更に彼女について調べてみると、面白いことが分かった。ポリドリの甥の一人、ウィリアム・マイケル・ロセッティは、叔父ポリドリの死後、叔父の手記を編纂して出版している。そこによせたウィリアムによる解説によると、マーティノーはかつてポリドリのことを愛していたそうだ*11。甥のウィリアムも伝聞だけであろうが、信頼性があるとみて紹介したのだろう。マーティノーはよくポリドリのことを思い出していたと解説するサイトもあることから*12、信ぴょう性は高いように思う。
閑話休題。ポリドリは8人兄弟の最年長となる子であるから、父ガエターノはポリドリには医者になってもらうことを強く要望した。そこでポリドリは、スコットランドのエディンバラ大学へ入学する。当時のエディンバラ大学は、当時のヨーロッパ圏及び英語圏の中において、屈指の医学研究の中心地だったという。だがポリドリは医者になる気は無かったし、気風の違うスコットランドの生活も合わなかった。祖父はイタリア人であるから、途中イタリア人の血として目覚め、当時まだ統一されていなかった「祖国」イタリアのために働きだしたいと、言い出すほどであった。だが結局父に見捨てられたくない想いから、妹のフランシスに弱音を吐きつつも、彼は勉学に励む。1815年7月、本来は半年かかる冗長な卒業試験をいくつも受けて、なんとか卒業にこぎつける。しかしその成績は、試験官である教授が「ただ合格したのではなく、全ての人の満足を満たして合格した」と、直々に賞賛の言葉を与えに来たほど、見事な成績を収めたという。卒業論文の内容もかなり良かったようだ*13。
その時の卒業論文の内容は、夢遊病と悪夢に関するもの。タイトルは”A Medical Inaugural Dissertation which deals with the disease called Oneirodynia, for the degree of Medical Doctor, Edinburgh (1815)”*14*15これが後に、ある人物の偉大なる小説の構成とアイデアに影響を与えることになる。そしてその小説は、彼の小説「吸血鬼」よりもはるかに有名になり、今の日本でも知られる作品となる。
若干20歳にて優秀な成績を収めて大学を卒業したポリドリだが、医師としてすぐに働くことはできなかった。というのも、当時のイングランドとスコットランドでは法律が違っており、26歳になってイングランドの試験にパスしなければ、ロンドンでは医師として開業できないという事情があった*16。そこでポリドリは、詩人として名高いジョージ・ゴードン・バイロンことバイロン卿の侍医として雇われることを選んだ。
前々回記事の終わり際にも述べたように、「吸血鬼」の作者・ポリドリのことを語るには、この主人であるバイロン卿のことを抜きにして語ることはできない。それもかなり深くバイロンという人物を知る必要がある。バイロン卿という人物は吸血鬼を知る上で、それほどまでに重要な人物なのだ。
ということで、ポリドリの主人、バイロン卿について解説していこう。
事実は小説より奇なり:詩人バイロン卿

(1788~1824)
バイロン卿はイギリスのロマン派の詩人。彼は良いとか悪いとか、そういった単純な物差しでは測れない、非常に複雑な人間性を秘めた人物だ。そこがバイロン卿という人物の面白いところである。
さて彼の作品は多数あるが、その中でも有名なものは、17世紀スペインの伝説上の人物をモチーフにした、「ドン・ジュアン」という詩だろう。ドン・ジュアンはフランス語の言い方で、英語ではドン・ファンと呼ぶが、バイロンの作品の場合はドン・ジュアンと呼ぶのが一般的なようだ。その「ドン・ジュアン」には「事実は小説より(も)奇なり」という有名な言葉が出てくる。日本では慣用句として使われるほど有名になったが、実はこれは日本語訳にする際の誤訳で、本来の意味とは違うそうだ。だがバイロンを一言で表すとしたら、まさに「事実は小説より奇なり」の一言に尽きる。それほどまでに破天荒な人生を送ってきたのが、バイロン卿だ。
バイロンの作風であるが、自分の体験に基づいたものが多い。現に彼は「私は自分の経験や下地がなければ、何事によらず詩う(うたう)ことが出来ない」と自ら述べている*17。そしてバイロンは、瞬時の感情を吐露する試作態度を好み、推敲というものを極度に嫌ったという。これに対してラフカディオ・ハーン(小泉八雲)は、「バイロンは自分自身の言葉を推敲しなかった詩人」だとして、批判的に評価している*18*19。ハーンは「原稿は9回書き直さなければまともにならない」と言っていたそうだから*20、バイロンの手法はハーンの美学に反するから、厳しくなるのだろう。
一方でバイロンを評価した人物は、なんといってもあのゲーテだ。ゲーテは「ロマン派は病気」だと言ってロマン派の作家には批判的であった。だがバイロンは別で「バイロン卿こそ、19世紀最大の天才である」と大絶賛している*21。実際、バイロンが36歳という若さで亡くなった時ゲーテは酷く嘆いた。そしてゲーテはあの「ファウスト)」の第二部において、バイロンをファウストの息子・ユーフォリアンとして登場させ、その死を哀悼している*22。他にもバイロンの劇詩「マンフレッド」は、あのチャイコフスキーやシューマンが曲を付けたほど。このように名立たる音楽家にも、その実力が認められていた。
幼少期のバイロン卿:逆境にめげない主人公
それではバイロン卿の生い立ちを説明していこう。バイロン卿は生まれつき肌が青白く、非常に類まれな美貌を持っていた(重要)。彼は当時イギリスで一番モテた男と言っても過言ではない。当然バイロンは女好きであったが、多くの女性が彼と関係を持とうとしたぐらいモテた。そしてその美貌は女性のみならず、男すらも魅了するほどで、美男子とも性的関係を持っていた(重要)。特にバイロン卿は美少年を愛した。バイロン卿を題材にした劇などでは「女よりも美少年の方が素晴らしい」なんて言わせるものもあるぐらいだ(その劇についてはこちらへ)。
バイロンを知る上でもう一つ言及しておきたいことは、生まれたときから右足に障害があったことだ。湾曲していたものと考えられており*23、右足は生涯にわたって引きずっていたとされる。バイロン卿の肖像画は全身はなくて上半身ばかり、足を描かれても右足が隠されているのは、足が悪かったせいだと考えられている*24。
性格面の方はというと、彼自身も言うように非常にむらっけのある性格だった。正義感に溢れ、物腰柔らかな好印象な面があるかと思えば、突如癇癪を起して当たり散らすなど、気性の激しい面もあった。一般庶民を気遣うかと思えば、極端な貴族尊重主義に陥るという、矛盾した言動をとることもあった。このようなバイロンの性格を形成した要因は、もちろん両親との関係や幼少時の経験が、大いに関係している。

ジョン"マッド・ジャック"バイロン
上記の肖像画からは想像できないが、バイロン卿の父ジョン・バイロンは美男子であったという。だが向こう見ずな行動をするギャンブル狂いのろくでなしで、借金をこさえてばかり。そして借金の都度、資産家の女と結婚、その資産を食い潰していくということをしていた為、「きちがいジャック」とあだ名されていた*25。英語wikipedia記事でもあだ名「マッド・ジャック」を紹介している*26。
さてこんな父であるから、バイロンにはオーガスタという腹違いの姉がいた。この腹違いの姉は、後にバイロンの人生に大きく影響を与えることになる。後年バイロンは、「父は女を破滅へと追いやるべく生まれついた人だった」と回想している。だがバイロン自身も父と同じく女好きになり、多くの女性を破滅へと追いやっていく人生をたどることになる*27。
そんな父はバイロンが3歳の時、36歳という若さで亡くなるが、実はバイロン自身も36歳で亡くなっている。そしてバイロンの娘も36歳で亡くなっている*28。36歳という年齢は、バイロン家にとって何かしらの因果があるのではないかと思わされる。
その後バイロンが10歳のころ、大叔父に当たる第5代目バイロン男爵が死んだことにより、ジョージ・ゴードン・バイロンはバイロン家の家長、第6代バイロン男爵となる*29。

バイロン卿の母・キャサリン・ゴードンは、小太りで美人ではなかったが、両親が死別したため多額の遺産を相続していた。そこを借金で困っていたジョン・バイロンが目を付けて結婚した*30。息子バイロンのことは当然母親として愛していた。だがキャサリンは、皿を噛み切ることもあるほどの癇癪持ちで、典型的なケルト人らしい気性の激しい性格でもあった。息子バイロンに対して、「バイロンの血を受け継いでいるから下品な子!」とか、「身障のガキ!」と罵ることも度々あったという。自分が足が不自由なのは、自分の出生時における凶暴な母親の愚かさにより生じたのであると、バイロンは信じ込むようになった。ただ、父も母も終生、心底恨むようなこともなかったという*31。
母を心底恨むことはなかったとはいえ、やはり足の件は気にしていたようだ。そして彼は負けず嫌いでもあった。足が不自由ながらも野原を走り回ったり、川を泳いだり、ボクシングに打ち込んだりと活発な面もあった。喧嘩も強く、「足の悪いバイロン」などと馬鹿にしたやつは、拳骨の雨を見舞ってやった。特にバイロンは正義感が強かったので、弱い者いじめは絶対許さず、いじめっ子に猛然と声を張り上げて抗議をする、もしくは徹底的に打ちのめした。そのため悪童からは「喧嘩バイロン」と尊敬された*32。この様にバイロンは、自身の弱点を跳ね除けていった。これは彼は天性の美貌を持っていて、普段は物腰も柔らかかったことも、身体の不具を帳消しにしたのだろうと考えられている。彼こそがまさしく「※但し、イケメンに限る」というやつだろう。
さてバイロンの人格形成を見るうえで、もう一人知っておかなければならない人物がいる。それは幼少年期のバイロンの乳母として仕えた、メイ・グレイという女性だ。この乳母は大酒のみ、好色、放蕩癖があるというとんでもない阿婆擦れ女で、バイロンに終生取り返しのつかない経験を与えてしまった。
バイロンの母キャサリンは癇癪持ちであったから、少年期バイロンは自然とこの乳母のことを慕うようになった。だがメイは、バイロンに骨が痛むほと打ち据えたり、バイロンの目の前で母キャサリンの悪口を言うなど、心も体も痛めつけた。メイの所業はこれだけではなく、他にも少年バイロンをを引き連れていかがわしい夜の酒場を飲みにつれていく、少年バイロンの部屋に下品な男を連れ込むなどする。挙句の果てには、少年バイロンを連れてベッドに飛び込み、馭者との情事を楽しむ様子を見せつけていたという*33。このようにもはや虐待行為をバイロンに行っていた。バイロン家の弁護士ジョン・ハンソンは、当時のバイロンとメイ・グレイの関係に驚き、母キャサリンに即刻この乳母を解雇するよう手紙を送っている。1821年の日記「断想」の中でバイロンは、「このメイと関係により、自分の性の目覚めはあまりにも早かった」と、自ら述べるほど。そしてこのことが広まると周囲の者に迷惑がかかるからということで、バイロンの死後、遺言に従った友人のホブハウスによって、このメイに関する事情が書かれた日記の大半は、焼却されてしまった*34。バイロン自身にとって、あまりいい思い出ではなかったことは明白だ。
以上がバイロンの人格形成に大きく関わった人たちだ。父からは天性の美貌を受け継ぎ、母からは気性の激しさを受け継いだ。そして乳母のメイ・グレイには、あまりにも早く性を目覚めさせられ、その結果父と同じく女好きになり、多くの女性を不幸にさせていくことになる。
放蕩三昧する大学時代のバイロン 男色にも目覚める

普通でない少年期を過ごしたバイロン。成長した彼はあの名門・ケンブリッジ大学に入学する。たがバイロンにとって学業はつまらなかったようで、遊蕩生活に耽る。バイロンが「ペイフィアンの女神たち」*35と呼んだ売春婦を不自由なく集めて、歓楽遊蕩三昧の生活にふけった。当然湯水のごとくお金を浪費していく。当然高利貸しに世話になるのは時間の問題だった。バイロンは高利貸しを吸血鬼呼ばわりしながらも、お金を借りていた。こうしてバイロンは負債を貯めていき、母キャサリンや姉オーガスタが金策に奔走することになる*36。
余談になるが、高利貸しなどを吸血鬼に例えることは、海外ではよくみられる。18世紀の西欧では、聖職者、啓蒙思想化、政治家、ついには女帝マリアテレジアや当時のローマ教皇も巻き込んで、吸血鬼の存在を議論する吸血鬼大論争が巻き起こった。その時、啓蒙思想家のヴォルテールは吸血鬼は迷信と切って捨てた。そして「吸血鬼とは高額の年俸を貰い、人民を食い物にしている修道士のことだ」と言った*37。1897年(明治30年)エッチ・ダブリュー・ウォルフ著「国民銀行論」(リンク先参照)という翻訳本でも、高利貸しを小説中に出てくる吸血鬼に例えている。
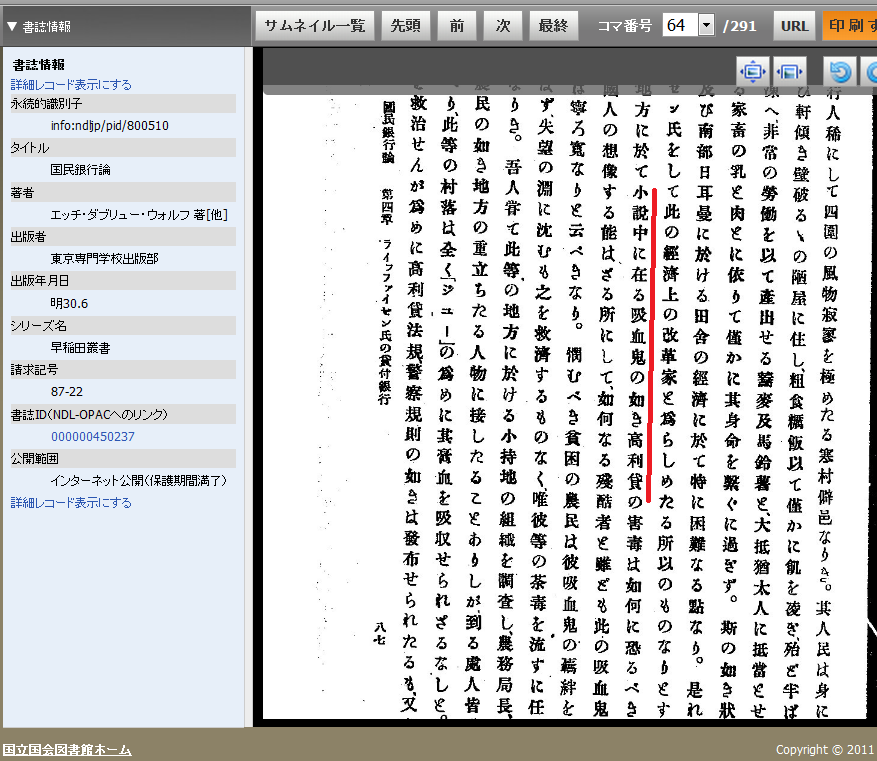
バイロンが高利貸しを吸血鬼に例えた当時、我々がよく知る貴族服を纏ったスタンダードな吸血鬼は、当然なことだがまだ生まれていなかった。それを作るのはこれより後、今回紹介するポリドリによってである。だが吸血鬼という存在自体は、18世紀の吸血鬼大論争をきっかけに、東欧の民間伝承に伝わる存在として知られていた。そして経済的吸血鬼という観念も18世紀から既にあったことが伺える。
話をバイロンの大学時代に戻そう。大学時代のバイロンは、父”きちがいジャック”と同じく遊蕩三昧にふけり、借金を増やしていくばかり。先ほどバイロンは母を心底終生恨むことはなかったと言ったが、この時期だけは母キャサリンとの関係が悪化する。遊蕩三昧や借金に対して文句をいう母に対して、意地悪い、蛇の如く絡みつく女、怪獣、毒樹、鬼ババア*38と、数々の罵詈雑言を浴びせていた*39。
さらにバイロンは遊びほうけるだけでなく、やりたい放題し始めた。具体的には、大学の寮内でクマを飼い始めた。バイロンは元来、動物好きであった。当初は犬を飼おうとしていたが、学則で禁じられていた。これに怒ったバイロンは抗議する意味も込めて、今度は熊をキャンパスに連れてきたという。バイロンは「犬はダメだと書いてあるが、熊はダメだとは書いてないから良いだろう」と屁理屈を述べた。これに大学は反論できなかった。さらにはクマを学生にする申請を提案したり、「クマはわが友故に同居す」と方言し、大学寮の一室で飼い始めた*40*41*42。俄かには信じられないが、バイロンの逸話として確かに残されている。ちなみにバイロンが熊を連れて来た日、当然なことだが大学は大パニックに陥ったという。
こうして利己的に荒れていくバイロンであるが、その一方で幼少時から見られる正義感に篤い面も覗かせていた。奉仕活動を続けるケンブリッジ大学の学友ジョン・エドルストンとフランシス・ホジスンのために、主に金銭面で多額の支援を行った*43。ホジスンはバイロンと手紙のやり取りをしていたのだが、そのバイロンに送った15通の手紙は2009年、277,350ポンド、日本円でおよそ4千万円で販売された*44。

(1781~1852)
もう一方の友人ジョン・エドルストンだが、バイロンは彼を愛するようになり、ゲイセクシュアルな関係となった*45*46*47。
ケンブリッジ大学でバイロンと友人関係となった人物で、もう一人言及しておきたいのが、ジョン・ケム・ホブハウスだ*48。彼とは生涯の親友と呼べる間柄となり、ホブハウスは何かとバイロンの世話を焼いてあげることになる。バイロンの遺言に従ってバイロンの日記の大半を燃やしたのもホブハウスだ。

(1786~1869)
学業を放棄したバイロンは、もっぱら処女詩集の出版に没頭した。そして1807年、自費出版ではなく、初めてタイトルに自分の名前を載せたという意味で最初の詩集となる「懶惰の日々(Hours of idleness)」を発表し、詩人としてデビューを果たす*49*50。
処女詩集はおおむね好評で『クリティカル・レビュー』誌と『マンスリー・レビュー』誌は若き才能を褒めた。だが翌年の1808年、『エディンバラ・レビュー』誌は酷評する。いや、もはや度を過ぎた個人攻撃であった。これにはケンブリッジ大学の学友や、同じ詩を嗜む詩友たちは、バイロンのために激昂した。温厚で知られる詩人ワーズワースでさえ憤慨したというのだから、よほどの酷評ぶりだったことが伺える*51。この酷評はバイロンにとってかなりショックだったのは事実なようだ。だがやられっぱなしのバイロンではない。翌年の1809年に「英国詩人とスコットランド批評家たちへ」という諷刺詩を匿名で出版、批評家たちに挑戦状をたたきつけた。これは予想を超えて大いに評判を呼び、第二版以降は署名入りで出版、幾度か版を重ねることとなった。こうしてバイロンは酷評の鬱憤を晴らした*52。
バイロンの人生に大きく影響を与えたグランドツアー
グランドツアー(大陸旅行)とは、17~18世紀のイギリスの裕福な貴族の子弟が、学業の終了時に行った大規模な国外旅行のこと。当時の裕福な貴族の子は、ほぼ必ず学業の締めとして行っていた。期間は時には数年に及ぶこともある。当時文化的な先進国であったフランスとイタリアが主な目的地で、一種の修学旅行ともいえる。お目付け役に同行してもらい、諸外国のことを学ぶ。とくにフランスは、イギリスの貴族階級の高貴さとはまた違った上品なマナーを身につけることができるという理由から、特に人気の地であった。最終目的地は常に古代ローマの遺跡、またルネサンスの中心地であったイタリア、ことにローマとみなされた。こうして諸外国のことや貴族のマナーを身に着けるのと同時に、快適な自宅暮らしから不便な旅の経験を経て、世間の厳しさを学んでいく、いわば貴族限定の成人の儀式とも言えるものだった。その他詳細は、wikipedia、コトバンク、ナショナルジオグラフィックの各記事を参照して欲しい。
1809年3月13日、バイロンは21歳の成年に達し*53、上院に席を置く。ホイッグ党急進派に所属した。だが退屈だったのか、貴族としての自覚が目覚めたのかは不明だが、バイロンはグランドツアーで各地を周ることを決意する。このグランドツアーこそが、後のバイロンの作品にも影響を与えていくことになる。危険な旅が予想されるため、旅立つ前にバイロンは決別パーティーを行う。メンバーはホブハウス、マシューズなどの友人たち、ペイフィアンの女神たち、そして飼っていた熊だ*54。本当に熊も参加していたらしい(当時の参加者たちは平常心でいられたのか、非常に気になる)。余談だが、後に友人関係となるトマス・ムーアの推測だと、この時参加したペイフィアンの女神(売春婦)たちは、メイドとしてバイロンに仕えた女たちで、その内ルーシンダという女性はバイロンとの間に一児をもうけ、年間100ポンド支給されていたという*55。
バイロンがグランドツアーに連れて行ったのは、友人ホブハウス、従者数名、そして美少年の小姓ロバート・ラッシュトンだ。当時のヨーロッパ大陸は、ナポレオン戦争の不穏な情勢下にあったため、グランドツアーの人気の地・フランスは避けて、ポルトガルのリスボンに向かい、そこからスペイン、イタリア方面へといく順路を取った*56。ジブラルタルへ到着した時、バイロンは老僕マレーと小姓ラッシュトンを英国へと送り返した。これは今後の旅が厳しく、肉体的に耐えられないだろうと予測されたからだ。というのもバイロンは通常のグランドツアーとは違って、オスマン帝国領にも旅をする予定でいた。当時のアルバニアなんかは未開の土地という認識だったから、危険な旅に同行させたくなかったのだろう。だが小姓ラッシュトンを送り返したのは、別の理由もあった。というのも当時のオスマンでは男色が盛んだった。実際、母キャサリンへの手紙には「美少年はトルコでは犯される危険があるのですよ」と書き送っている*57。大学時代のバイロンは母を口汚く罵っていたが、手紙を書いているあたり、この頃にはわだかまりは解けてきたように思われる。

オスマンではキョチェク(芸能者)やテッラク(三助兼マッサージ師)に携わる少年が少年売春に携わった。美少年の踊り子を巡る競争が過熱、問題になるほどであったそうだ。こうしたオスマンの男色事情は、当然キリスト教徒から度々非難の対象となった。後にコンスタンチノープル(イスタンブール)でキョチェクの踊りをみたホブハウスも「ぞっとするほどに汚らわしい」と評価した*58。ホブハウスの評からも、当時のオスマンでは男色が盛んだったことが伺える。

老僕と小姓を送り返したあと、バイロンはアルバニアへと到着する。何度も見せた上記の肖像画、これはアルバニアの民族衣装を着たものだ。右手に持っているものは、恐らくアラブのダガー、シャンビーヤだろう。こうしてバイロンは様々な文化に触れていく。
アルバニアを旅したバイロンは憧れの土地、ギリシアのアテネに到着する。ここでバイロンは14歳の少年、ニコロ・ジローと同性愛な関係となる*59。このニコロ・ジローという少年、私は最初そんなに重要な人物だとは思いもしなかったが、実は海外の学者や伝記作家の関心を集めている存在だった。その証拠に英語wikipediaにはニコロ・ジローの専用記事が作られている。ニコロとは純愛的な関係だったと考えられている一方、性的関係があったとも考えられている*60。
ギリシアのアテネはバイロンが憧れた土地であるが、そこでのそこで見たアテネの惨状にバイロンはショックを受ける。当時のギリシアは自らの宗教は守りつつもオスマンの支配下で、国民は奴隷扱いだった。有名な国宝は剥奪や破壊の憂き目にあっていた。又は英国の金持ちが買い叩いていた。お金を出してくれるので貧しいギリシアの国民は、むしろ喜んで売っていた。こうした惨状にバイロンは義憤を掻き立てられ、後の人生にも影響してくる*61。
バイロン卿は一度アテネを離れて、テネドス島に入る。そして何を思ったのか、流れが急なダーダネルス海峡に飛び込んだ。そして海峡を泳ぎ切った。泳いだ理由は、恋人のヘーローとの逢瀬のために毎晩荒海を泳いだと伝えられるギリシャ神話の人物、レアンドロスに敬意を表してのことだそうだ。後年発表した詩には「名誉の為」とも書いてある。ダーダネルス海峡は幅が1.6km程であるが、海流の流れが速いので最終的には6.5km程泳ぐことになる。こうしてバイロンは2013年時点で、世界海峡横断水泳の偉業を達した5人の内の一人にも数えられることになる*62*63*64。

「へレスポント海峡を泳いだ後、漁師の家で休憩するバイロン卿」 1831年
作・ウィリアム・アラン
※へレスポント海峡とは、ダーダネルス海峡の古い呼び名
この後はコンスタンティノープル(イスタンブール)へ行き、その景観を楽しむ。だが、死体をかじる犬などに、不快感を覚える出来事もあった。ガラタでは売春も行う少年の踊り子を見たホブハウスは、男色を想起してか吐き気を催すほど不快感を覚えた。トルコでは女性と関係をもつこと、ラーラ(随行の守護者)と特別な関係を持つことは禁じられたため、バイロンは禁欲生活を強いられた*65。
バイロンはギリシアへ戻る。ここでホブハウスは英国へ帰国する。借りた家だが、家主の母の権利として、バイロンは娘を結婚相手として押し付けられるか、もしくは結婚の代わりに娘を金で買わされるかの二者択一を迫られた。そのためキャピュチン女子修道院での生活を選ぶ。ここでバイロンはギリシアの青年、ジョージオウとねんごろの仲となる。女子修道院での生活は、バイロンに同性愛的な感情を掻き立てた。というのも西欧の少年たちのための学校でもあって、バイロンは子供たちと一緒に遊んだようだ*66。
こうして生活しているある日、バイロンはショッキングな事件に出くわす。人だかりができて何やらただ事ではなさそうだったので、バイロンは官憲に話を聞いた。彼らが言うには「トルコの娘が異教徒と暮らしていたことが発覚したので、袋の中に入れて今まさに海へ投げ込もうとしているところだ」ということだった。正義感が強いバイロンは官憲に交渉して娘の命乞いを行い、救い出す。そしてすぐさま修道院へと送って上げた。だが既にリンチを受けていたのであろう、その娘はその後すぐに息を引き取ってしまった*67。この出来事は後のバイロンの作品に影響を及ぼすことになる。
こうして旅を続けたバイロンは、1811年7月にグランドツアーを終える。戻ったとき、母キャサリンは死んでおり、大学時代同性愛関係となったエドルストンも、胸を病み他界していた。このグランドツアーによりバイロンは、ギリシアを第二の故郷と思うようになった。そしてそれが、後のバイロンの人生に大きく関わってくることになる。
ある日、目が覚めたら有名人になったバイロン
グランドツアーの後、バイロンは後に後援者でバイロンの伝記を書くことになる、詩人のトマス・ムーアと知り合いになる。このムーアは今は知名度は薄れてしまったが、あのゲーテがバイロン、サー・ウォルター・スコットと並んで三大詩人と呼んだほど、当時は評価された詩人だった*68。そんな詩人をバイロンは「イングリッシュバーズ」誌において暴言、酷評を行う。これに激怒したムーアは決闘を申し込もうとしたほどだ。でも結局はバイロンにほれ込み、他の知り合いを集めて四人会を結成する。その中の良さは古くからの友人ホブハウスも羨んだほどだ*69。このムーアと知り合いになったことにより、バイロンは湖水詩人であるワーズワースやコールリッジと知り合うきっかけを得る。バイロンの死後ムーアは、バイロンの伝記を書くことになる。

(1779~1852)
バイロンは詩を書く傍ら、1812年に若き貴族議員として政界に進出する。この時期のイギリスだが、産業革命の真っ只中。つまり機械化が進み、労働者の失業が社会問題となっていた。この時期の経営者は労働者を食いものにしていて、労働者は泣き寝入りするしかなかった。だが一部の過激派、ラッダイト暴徒は工場の機械を破壊するなどの行為に及んでいた。つまりラッダイト運動が盛んだった。政府はこのラッダイト暴徒対策の為に、彼らを処刑できる法案を通そうとしていた。だが少年期から正義感に溢れていたバイロンは、人道を無視するこの処刑案に猛然と反対する。労働者が餓えに苦しんでいることを、理路整然と激しい口調で演説した。このバイロンの処女演説は、在野党からは拍手喝采を、トーリー党議員からは罵声を浴びるほど場を熱くさせた。演説後、握手を求める人も多くいた。この件でバイロンの名声は、一気に世間に広がることになる。バイロンは政治家のままなら祖国を変えるであろうとか、政治家は詩人以上に天職であったかもしれないなどと評価されていたのにも関わらず、僅か16か月で政界から身を引くこととなる。これは激しく人権を追求する傍ら、極端にまで貴族的基準も尊重していたのでその間で板挟みとなり、批判の集中砲火を受けたことが原因だと考えられている*70。いつの時代も、ダブルスタンダートには厳しいようだ。
さて政界に進出した同じ年の1812年、バイロンは一つの作品を発表する。それが「チャイルド・ハロルドの巡礼」という詩の第1篇と第2篇だ。これは前年までのグランドツアーを体験をもとにして作られた作品で、日本語訳もある。この作品の生の倦怠と憧憬を盛った詩風と異国情緒が時代にマッチし、大評判となる。瞬く間に1ヶ月で5000部も売れた*71。これは当時としては破格の部数だ。
さて、この「チャイルド・ハロルドの巡礼」という作品であるが、主人公はバイロン自身を自己投影したキャラクターだ。こうした特徴をもつキャラクターを説明する言葉として、”Byronic hero:バイロン的主人公”*72という言葉まで生まれた。英語wikipediaにも専用記事が作られているほどだ。バイロニック・ヒーローの特徴は本当に色々あるが、例を挙げると次の通り。
尊大・冷酷
洗練されていて教養がある
神秘的、魅力的、カリスマ性がある
誘惑する力や性的魅力を有する
社会的・性的に優位な立場にある
社会制度や規範を嫌う
通常「ヒーロー」とは結びつかない陰の面がある
黒歴史があったり、名もなき犯罪で苦しむ
階級や特権に敬意を表さない
通常「ヒーロー」とは結びつかない陰の面がある
むらっけのある性格
他にも色々あるが簡単に言えば、「たとえ間違った行動をしても賞賛される悲劇的な人物」というように紹介される。そしてバイロン的主人公は、つまるところバイロンの人格(ペルソナ)を表しているとも言われている。こうしてみると、二次創作でオリジナルキャラや自己投影したキャラを優遇しまくる俗語メアリー・スーと似た特徴をもつ。ただメアリー・スーとは違い、バイロニック・ヒーローはネガティブな印象はないようだ。それは当時のバイロンは、英国で一番女性にモテた男であるからだろう。それどころか、男すらをも魅了するほどだった。チャイルド・ハロルドの巡礼以降、バイロンの作品の主人公は、こうしたバイロニック・ヒーロー:バイロン的主人公を特徴を持つようになる*73*74*75。
ラッダイト暴徒に関する処女演説で、既に有名になりつつあったバイロンだが、この「チャイルド・ハロルドの巡礼」の出版により、バイロンの名は瞬く間にイギリスに広まった。1812年の春、バイロンは若きプリンスとして社交界に進出する。その時のことをバイロンは後年こう振り返っている。「ある朝目が覚めると、自分は有名人になっていた」と。この名句もバイロンが放った言葉だ。ともかく1812年の春より、バイロンは若きプリンスとして社交界デビューするが、パーティーに出ると色んな人が「バイロン、バイロン」と言って近づき、席に座る暇がなかったほどだという。そして生来の美貌も相まって、多くの女性がバイロンに群がり集まった。そして名だたる女性と恋愛遍歴を飾ることになる*76。こうして父マッド・ジャックと同じ道を辿っていくことになる。



(1785~1828)
日本語wikipedia 英語wikipedia

さてバイロンは名立たる女性と関係を持っていくが、その中の一人が、若きヴィクトリア女王の助言者として注目を浴びていたウィリアム・ラムの若妻であり、26歳の美貌の才媛、レディ・キャロライン・ラムだ。1807年に息子を、1809年に娘をもうけるも、息子は精神的な病で29歳で死亡、娘は生まれてすぐに夭折した。夫が政界に進出すると構って貰えなくなった。そうした中、キャロラインはバイロンと出会った。当時の社交界は、不倫や愛人関係は、ある程度は許容されていた。キャロラインは1812年に最初バイロンと会った時、「あなたには興味ないわ」と言わんばかりに、バイロンの目の前でこれ見よがしに踵を返した。バイロンは当時のイギリスで一番モテた男といっても過言ではない。本人もその自負があったのか、誇りと自尊心を傷つけられたバイロンは、急激に彼女に興味を持つことになる。その日のキャロラインの日記には、こう書かれていた。「どうかしているわ。いけないことだわ。彼に近づくのは」。キャロラインは、バイロンの「チャイルド・ハロルドの巡礼」を貪るように読みふけっていた。そしていち早く、バイロン卿とチャイルド・ハロルドが同一人物であることを読み取っていた*77。
バイロンとチャイルド・ハロルドが同一人物であることを早急に読み取ったのは、キャロラインだけではない。キャロライン・ラムの従妹にて、後にバイロンと結婚することになるアナベラ・ミルバンクも、チャイルド・ハロルドはバイロンの自己投影したキャラであることを読み取っていた。

(1792~1860)
一般的に、略したアナベラの愛称で呼ばれる
アナベラは知的な女性で、とくに数学を専攻していた。これが後にバイロンとの間の娘に多大な影響与え、ひいては技術の進歩に大きな爪痕を残すことになる。
バイロンが、キャロラインと出会った初期のころ、ダンスの早朝練習会でアナベラと出会った。足の悪いバイロンは上手に踊れないのでこの時のバイロンの心情は、官能的に踊る美女より慎ましやかな令嬢のアナベラに惹かれた。彼女もバイロンに惹かれた。しかしこの出会いが後に彼女に悲劇をもたらすことを、アナベラはこの時は思いもしなかっただろう*78。
さてバイロンは当時英国で一番モテた男だ。当然女には不自由しない。だからバイロンは春に出会ったキャロラインには、夏にはもう飽きてしまった。当然バイロンは、他の女と出会うようになる。それを見たキャロラインは猛烈な嫉妬に駆られる。バイロンが他の女と話す場面を見ると杯をかみ砕いたり、人前であからさまに陰毛(ビュービック・ヘア)を数本抜き取りバイロンに与えて、自分もお返しをくれるよう強要する、変装してバイロンの部屋に忍び込んだり、駆け落ちを迫ったりもしだした。ついには愛が憎しみに転じたようで、キャロラインは大勢の人々を集めて、目の前でバイロンの人形を呪いながら燃やし続けた。だがやっぱり愛も残っていたようで、その後もバイロンに付きまとう*79。以後、キャロラインはバイロンに対して異常な執念を見せるようになる。
バイロンがこの嫉妬に狂ったキャロラインとどうにか絶縁出来るのは、キャロラインがオックスフォード伯爵夫人に手紙で、疑惑の怒りと非難の罵声を浴びせた後だ。この伯爵夫人は、キャロラインの後にバイロンが作った愛人だ。その手紙の内容だが、あのゲーテやシラーの初期の作風、シュトゥルム・ウント・ドランク(疾風怒濤)のスタイルで長々と書かれていたという。まるで「私は教養があるのよ」と言わんばかりである。そして同時期、キャロラインはバイロンの髪を一房送るように求めるが、バイロンは代わりにオックスフォード伯爵夫人*80の髪を送り付ける。こうしてバイロンは、一応はキャロラインと絶縁することができた*81。

ジェーン・エリザベス・ハーレー(旧姓スコット)(英語wikipedia)
(1774~1824)
※もともとオックスフォード伯爵の爵位の継承者が、別に存在していた。その継承者が出てきた時に備えて紋章院がモーティマー伯とセットにしたらしいと、とある方から教えて頂きました。
ここまでご覧頂きまして、ありがとうございます。長くなりましたので、一旦ここで区切らせていただきます。次回は、バイロンの結婚から追放、そしてバイロンの吸血鬼作品「異教徒」について解説していきます。
この記事は2020年2月1日にニコニコの「ブロマガ」で投稿した記事を、加筆訂正したものです。元記事は下記のアーカイブよりご覧ください。
投げ銭(支援)して頂ける方はこちらへ www.vampire-load-ruthven.com
お勧めの吸血鬼解説本です。見た目とは違い、内容は本格的です。
ランキング参加中!クリックして貰えると嬉しいです。![]() にほんブログ村
にほんブログ村
![]() 人気ブログランキング
人気ブログランキング
次の記事➡バイロンの吸血鬼の詩「異教徒」とバイロンの祖国追放
*1:ジャック・サリヴァン編「幻想文学大辞典」:高山宏ほか編集・翻訳/国書刊行会(1999) p.552
*2:荒俣宏・編「怪奇文学大山脈(1)」:東京創元社(2014) pp.400-402
*3:牧野陽子「ラフカディオ・ハーン 異文化体験の果てに」:中公新書(1992) p.160
*4:19世紀前半におけるヴァンピリスムス -E.T.A. ホフマンに見るポリドリの影響-
森口大地 京都大学大学院独文研究室 2016/01 p.69
*5:同上
*6:「幻想文学大辞典」 p.552
*7:”Gaetano Polidori” 英語wikipedia記事
*8:同上
*9:クリストファー・フレイニング「悪夢の世界 ホラー小説誕生」:荒木正純ほか訳/東洋書林(1998) p.10
*10:Literary Norfolk 項目:Harriet Martineau(海外サイト リンク先参照)
*11:The Diary of Dr. John William Polidori, 1816, Relating to Byron, Shelley, etc.
ウィリアム・マイケル・ロセッティ編/プロジェクト・グーテンベルク(1911年出版)
*12:Literary Norfolk 項目:Polidori
*13:バイロンとポリドリ:ヴァンパイアリズムを中心に 滋賀医科大学 相浦玲子 p.10
*14:「幻想文学大辞典」 p.552
*15:"John William Polidori" 英語wikipedia記事
*16:バイロンとポリドリ:ヴァンパイアリズムを中心に p.10
*17:楠本晢夫「永遠の巡礼詩人バイロン」:三省堂(1991) p.19
*18:同上 p.49
*19:「バイロンの解説からみるハーン」 その1リンク その2リンク ※2分割
島根大学外国語教育センター 伊野家 伸一
*20:「永遠の巡礼詩人バイロン」 p.ⅴ,p.10
*21:「永遠の巡礼詩人バイロン」 p.ⅴ,p.10
*22:同上 p.4
*23:「永遠の巡礼詩人バイロン」 p.22
※当時は左足が悪いせいだとする医師もいた(参考:同上 p.29)
*24:金原義明「世界文学の高峰たち 第二巻」 :明鏡舎(2016) リンク先Googleブックスサンプル参照
*25:「永遠の巡礼詩人バイロン」 p.13,P.23
*26:"Lord Byron" 英語wikipedia記事
*27:「永遠の巡礼詩人バイロン」 p.24
*28:同上 p.25
*29:同上 p.28
*30:同上 p.13
*31:同上 pp.23-25
*32:同上 p.24,pp32-34
*33:ニューヨーク・タイムズのこの記事によれば、バイロンが9歳の時のこと。
*34:「永遠の巡礼詩人バイロン」 pp.30-31
*35:ペイフィアンの女神とは淫らな女の意味で、当時の売春婦を指す 参照:「永遠の巡礼詩人バイロン」 p.56
*36:「永遠の巡礼詩人バイロン」 p.44
*37:種村季弘「吸血鬼幻想」:薔薇十字社版(1970) pp.43-44、河出文庫版(1983) pp.58-60
*38:「永遠の巡礼詩人バイロン」p.48には確かに鬼婆とあるが、鬼と翻訳するのは良いのだろうかと疑問に思う。
*39:「永遠の巡礼詩人バイロン」 p.48
*40:”Lord Byron” 英語wikipedia
*41:"The Vintage News"より「犬は許可されていなかったため、クマを飼い始めたバイロン」という記事
*42:「永遠の巡礼詩人バイロン」 p.58
*43:「永遠の巡礼詩人バイロン」 p.47
*44:"Francis Hodgson" 英語wikipedia
*45:「永遠の巡礼詩人バイロン」 p.56
*46:"Gay History and Literature"より「バイロン卿ゲイ愛の手紙」の記事より
*47:カリフォルニア州立大学ロングビーチ英語学科クリフトン・スナイダー博士のサイトより
*48:ホブハウスの名前の日本語表記は定まっていなくて書籍によって違うが、今回はジョン・ケム・ホブハウスを採用した。
*49:”ジョージ・ゴードン・バイロン” 日本語wikipedia記事
*50:「永遠の巡礼詩人バイロン」 p.49 ※ここでは「懶惰の日々」ではなく「懈怠集」と訳されている。
*51:同上 p.52
*52:同上 p.53,pp.59-61
*53:1960年代まではイギリスの成人年齢は21歳、参考:”成年”wikipedia記事ほか
*54:「永遠の巡礼詩人バイロン」 pp.67-69
*55:同上 p.96
*56:日本バイロン協会の「詩人バイロンについて」の記事より 元サイトがなくなったようなのでリンク先はアーカイブ
*57:「永遠の巡礼詩人バイロン」 p.78
*58:”イスラーム世界の少年愛” 日本語wikipedia記事
*59:English Poetry and Literatureより、バイロンの解説ページ(日本語のサイトです)
*60:ちなみにニコロの英語wikipediaには次のようなことが書いてある。あくまで従者の噂にしかすぎないが、バイロンがある日、ニコロと一緒に医者を訪ねたらしいが、それはニコロの肛門破裂に関する相談だったのではないかと言う噂が流れた。あくまで従者の噂にしか過ぎないことを念を押しおこう。(でも本当だったら、激しすぎやろ!)
*61:「永遠の巡礼詩人バイロン」 p.87
*62:同上 pp.89-90
*63:歴史スター名鑑より「バイロンは足が不自由なのに水泳が得意だった!」
*64:ナショナルジオフラフィックより「海峡横断水泳、5つの歴史的偉業」
*65:「永遠の巡礼詩人バイロン」 p.91
*66:同上 pp.91-93
*67:同上 pp.93-94
*68:評論家・翻訳家の山形浩生のサイトより、トマス・ムーアの記事
*69:「永遠の巡礼詩人バイロン」 pp.102
*70:同上 pp.103-105
*71:同上 p.106
*72:同上 p.110
*73:"Byronic hero" 英語wikipedia
*75:読書に使う「憂いのふるい」より、Byronic hero
*76:「永遠の巡礼詩人バイロン」 pp.160-107
*77:同上 pp.107-110
*78:同上 pp.112-114
*79:同上 pp.111-112
*80:オックスフォード伯爵夫人の名前の呼び方は、書籍によってさまざま。「永遠の巡礼詩人バイロン」ではオックスフォード伯爵夫人だが、ジェーン・エリザベス・ハーレーと紹介していたり、旧姓のジェーン・エリザベス・スコットと紹介する書籍も見かけた。
*81:同上 pp.119-120
